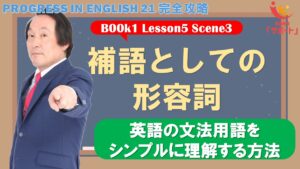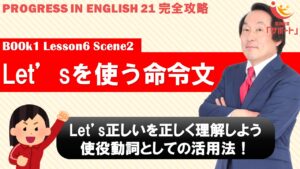命令文【Progress Book1 6-1】
命令文は動詞原形で始まります。それについて詳しく見ていきましょう。
命令文の基本
命令文は、英語で何かを頼んだり指示したりする場面で使用されます。通常、命令文は動詞原形で始まります。例えば、“Close the door.”(ドアを閉めてください)といった文です。しかし、注意が必要なのは、“Please”(お願いします)などの丁寧な表現を付けると、命令文がより穏やかな頼みごとに変わることです。“Please”を加えると、命令というよりも頼みごととして受け取られます。ただし、目上の人への頼みごとやフォーマルな場面では、命令文ではなくより丁寧な表現が適しています。
人との関係による違い
英語の命令文は、相手との関係によっても異なる場合があります。親しい友人やクラスメイトとの間では、命令文を使って頼むことが一般的です。しかし、目上の人に対しては、より丁寧な表現を用いることが礼儀とされています。したがって、相手との関係に応じて適切な表現を選ぶことが重要です。
否定命令文の表現
時折、何かをしないように頼む必要があります。この場合、否定命令文を使います。例えば、“Don’t watch TV.”(テレビを見るな)という文です。“Don’t”は“do not”の短縮形で、否定を表します。このように、否定命令文を使う際には、“Don’t”を動詞の原形に続けて使用します。ただし、シチュエーションによって訳し方が異なることもあるので、文脈に注意が必要です。
自動詞と他動詞の違い
英語の動詞は、自動詞と他動詞に分かれます。自動詞は目的語を必要とせず、文が単独で完結します。例えば、“He looked.”(彼は見た)という文です。一方、他動詞は目的語を伴う動詞で、文に対象が含まれます。例えば、“He met a friend.”(彼は友達に会った)という文です。自動詞と他動詞の区別は、文法的にも意味的にも重要です。しっかりと理解しましょう。
PROGRESSへの注意
最後に、英語の教材であるPROGRESSについて触れておきましょう。PROGRESSは非常に有用な教材ですが、自動詞と他動詞の区別に関する情報が不足していることがあります。自動詞と他動詞の理解は英語学習において重要な要素です。PROGRESSを使用する際には、この点に注意して学習を進めることをおすすめします。
以上が命令文についての基本情報です。自動詞と他動詞の違いにも注意を払いながら、英語を習得していきましょう。