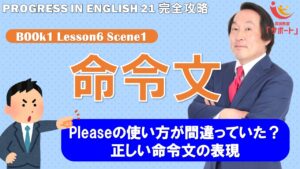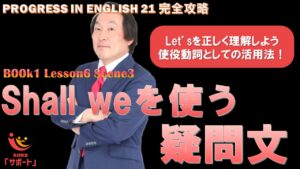Let’sを使う命令文【Progress Book1 6-2】
Book1 Lesson6シーン2:Let’sを使う命令文の続き
このセクションでは、「Let’s」を使う命令文について詳しく説明します。中学1、2年生の皆さんにとって、この単元は難しくないと思います。
命令文の基本
最初に考えるべきは、命令文の基本原則です。命令文は通常、動詞原形で始まります。例えば、次の文をご覧ください。「[Please]を無視して、『Open your books.』」。これは命令文です。基本的な原則は何でしょうか?正解は、動詞原形で文を始めることです。具体的には、「本を開きなさい」と指示しています。日本的な教え方では、「[Please]」を前に付けて、「『Please Open your books.』」とも言います。これで「本を開いてください」というより丁寧な頼みごとになります。逆に、「don’t」を付けると、「『don’t open your books.』」となり、「本を開かないでください」という意味になります。
Let’sを使った命令文
ここからは、「Let’s」を使った命令文について考えてみましょう。「Let’s」は、「何々にしようぜ」という意味になります。「Let’s go」は「行きましょう」という意味です。「go」も動詞原形であることに注意してください。例文を見てみましょう。「1番は『Let’s begin a new lesson today.』」、日本語では「新しいレッスンを始めましょう」と言いますが、「新しいレッスンに入りましょう」と表現した方がより綺麗に聞こえるかもしれません。
Let’sを使った否定の命令文
「Let’s」を使った否定の命令文もあります。「Let’s not 動詞原形」と覚えましょう。「Let’s not stay inside.」は「中に留まるなんてやめておこうぜ」という意味です。日本語では「外に出ようぜ」が一般的かもしれませんが、英語を使う人々はこうした言い方もします。逆に、「しないでおこうぜ」という場合は、「Let’s not 動詞原形」を使います。
第5文型
中学3年生以降、学校によって中学2年生で学ぶこともあるかもしれませんが、第5文型と呼ばれるものが存在します。しかし、実は「Let’s」を使った命令文については、少し誤解があります。この誤解は、中学1年生に正確な説明をしても理解が難しいため、一時的に習得して、後で訂正されることが多いです。英語の学習は段階的に進むものであり、理解が難しい部分は徐々に説明が追加されることがあります。
「Let’s」は動詞原形の前に「Please」や「don’t」を付けるようなものではありません。実際には、「Let」が動詞原形です。英語の命令文は動詞原形で始まります。この「Let’s」は、「私たち」を表す「us」の略語です。実際には、「Let 動詞原形」という形をとり、人々に何かをさせるか、何かをする許可を与えます。使役動詞を習ったことがある方は、ここで気付いたかもしれません。使役動詞は「Let 人 動詞原形」の形を持ち、人々に何かをさせる許可を与えます。この事実を覚えておくと、文法の理解が深まります。
中学3年生ぐらいから、英語の学習はより詳細な領域に入っていきます。これらの概念が理解できるようになるのは、中2や中3の頃かもしれません。英語は段階的に学んでいくものなので、焦らずに進めましょう。
Let’sを使った例
最後に、こちらの例文も「Let’s」を使った命令文です。動詞原形は「Let」の後に続きます。「Let us go」や「Let it go」のように、この「Let’s」も同じ文法構造を持っています。ただし、「Let’s」は「私たち」の「us」を短縮した形です。「Let 目的語 動詞原形」は「これがこれするのを許可する」ことを意味し、文法的には命令文です。この事実を覚えておけば、「Let’s」を理解するのは簡単です。